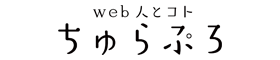ちゅらぷろインタビューvol.7 人生のターニングポイント、これから。。。夢
一般社団法人ある 代表 たなはらきみえさん

自己紹介
皆さんこんにちは。一般社団法人あるの棚原喜美枝と申します。
一般社団法人「ある」は「あるがまま」を受け入れる、その存在そのものを認めていくっていうことを目標にしている団体です。
27年前に「私らしいお産を考える会」という任意団体がスタートなんです。当時、20代で、自分の子供の出産を控えていて、お産の選択肢を広げる目標で始めました。実はお産って選べるんですね。選択肢があるっていうのはその人を強みに持っていける、豊かにするなっていうのを感じていました。
妊娠してはじめて、医療に守られた中で医師に言われるがままにただ「産めばいい」っていうのがすごく嫌で怖かったんですね。それでだんだんと自宅で出産したいって思うようになりました。
みんなで輪になって自分のお産体験を語る。そうすると話を聞いた人たちがそれを元にまた自分のお産を強みに変えていくような循環をずっとやっていて、今に至っているんですね。そんなこんなで2020年に法人化して、今ちょうど4年経ったところです。
今の仕事をするきっかけ
今の仕事をするきっかけになったのは、遡っていくと私、4人兄弟の1番上なんです。2歳下に重い知的障害の弟がいまして。うちの両親はその弟を追っかけることが子育てのメインでした。
上に生まれた私はほとんど目もかけてもらえない、手もかけてもらえない。弟は山猿みたいな、言葉も発せないような知的障害がありましたから、全部弟に親の愛情が集中していったわけですね。
そうすると私は寂しい子だったんです。かまってもらえない、見てもらえない。2歳しか変わらない弟に全部持ってかれてっていうような経過があって。
そんな私を癒してくれたのは母の妹、おばさんでした。私のことをすごく可愛がってくれたんです。県外に住んでいたんでたまにきて、本を読んでくれるわけ、絵本をね。その絵本を読んでくれた経験がすごく私の原体験になっていて、おばさんが私の憧れの人でした。おばさんは保育士だったんですよ。
おばさんみたいな保育士になりたいなっていうのがずっとあって、保育士になりました。
施設での経験

保育士の実習で1番最初の実習が児童養護施設だったんですよね。その児童養護施設での実習は、まだ19歳の私を1週間箱詰めにしといて、住み込みの実習をさせるわけです。初めてなのでもうとにかく辛くてたまらない。何をどうしたらいいかわかんなかったです。
そんな中入所している子供が言ったんですよ。「どんなに貧乏でもいいから、俺は父ちゃんと暮らしたかった」って。でその言葉がずっとあって、子供ってそっか、シンプルに親と暮らしたいよねっていうのがずっとありました。
私も元々寂しい子供時代の体験がありますからそこがうまく重なって、「そうだ、施設の職員になろうと決めて施設の保育士になったわけです。
そっから20年、もうとにかく児童養護施設の子供たちと共に過ごし追いかけることに夢中になっていた時期がありました。そこで20年保育士として勤めていたんですけど、私の原体験には寂しい気持ちがあるから、施設の運営とかに対して色々ストレートに言ったり行動したりするんですよ。
人生の転機

それでちょっとめんどくさい人だったんで、法人が持っているもうひとつの障害福祉サービス事業所に人事異動になっちゃったんです。私がやりたかったことは子供との向き合いなのに、なんで私をその障害福祉に行かせるんだとあばれました。
そもそも子供の時に知的障害のある弟に全部愛情持ってかれたっていう経験があるんで、弟のことなんか大嫌いだし、そんな知的障害のある人の相手なんか絶対嫌だっていうので、もうものすごく暴れました。
もう「やだやだ」て暴れて、ものすごく暴れて。上司にもこんな人事異動はありえないと言って立ち向かったけど、業務命令なので異動するしかなかったわけです。
ところがやさぐれていた私を、その知的障害のある40名の利用者さんがものすごく歓迎して迎えてくれました。そのすごく歓迎して迎えてくれた姿が、こんなにやさぐれてる私を彼らはまるごと受け入れてくれる初めてのあったかい経験をしました。もうそん時に本当に「皆さんごめんなさい」て思いました。
私の「ごめんなさい」から始まった障害福祉を8年やらせてもらいました。
そこでもやりたいことをいっぱいさせてもらえました。障害があってもなくても彼らのやりたいことを職員は「察する」ことから始まるんですね。察してそれを形にしていくっていうことを彼らすごく喜ぶんですよね。「ああ、それそれ」っていう風なサインが返ってくる。
だから、障害のある人たちを舞台にあげて歌も歌わせましたし、ダンスもしました。そうやって皆さんから見てもらえるっていうのが彼らのすごいモチベーションになっていくし、私もすごく楽しかった。
現在の活動へ
それでも、ずっと児童養護施設の子供たちのことが頭にあるわけですよ。そんな時ににじのはしファンドの糸数さんから、にじのはしファンドは給付型の奨学金を子供たちに出して、大学や専門学校に行けるように支援している団体です。
充分な奨学金を出しているのに、子供たちが途中退学をしてしまう。でそれがなぜだろうっていうのが糸数さんの悩みでした。
それを私と「どうしようか?」って考えていました。「お金をあげるだけじゃだめなんだよ。集まる場所があって、日常的な不満や弱音も吐き出す場所があった方がいいから食事会をしよう」ていうので、週に1回の「金ちゃんラーメンの会」を始めるようになったわけです。
集まった若者たちに「施設にいる時に何が1番美味しい料理だった?」って聞いたら、子供たちが「台風の時に食べたインスタントラーメン」って言ったんですよね。
施設って栄養士がついていて1日3食365日栄養価計算がされていて、お野菜もたっぷり、海藻もある、お肉もある、お魚もあるっていうような食事が3食出されるわけですよね。
ところが台風の日はメニューが想定されてないから、カップラーメンが出るんです。そこで食べるインスタントラーメンがごちそうだっていうのは本当によく分かります。学校お休みになるし、ワクワクする。当時ね20名ぐらいの子供を職員4人が交代でみてました。だから施設は24時間営業だから、1日をほぼ1人で見るんです、夜も昼も。
大きなお鍋にお湯を沸かしお玉でラーメンにお湯を注いでね食べたのがすごいいい思いでです。
こどもたちのそのラーメンの味、私も分かるなと思いながら毎週の食事会を始めたのが、今に至る感じですね。障害福祉サービスの仕事をしながらアフター5で2週に1度「金ちゃんラーメンの会」をやってるうちにアフターケアが県の委託事業になって、職業としてできるようになったので、施設を思い切ってやめて今に至っています。
これからのこと、夢
親支援ってとっても大事だなと思ってるんです。若い子の伸びしろってもう計り知れないですよ。子供のためだったら頑張れるっていう子も多いので、子供を安全安心に預かる場所があって、それを地域にいっぱい広げていくと、もう施設なんかいらなくなるんじゃないかなって思います。
里親さんたちが私のとこに結構関わってくれてるので、その里親さんたちが1泊でも2泊でもショートステイって言うんですけど、親が大変な時に1週間2週間お泊まりオッケーだよって言ってくれるおばあちゃん的な存在が地域にいっぱいいると、すごくこの沖縄、住みやすくなる、子育てしやすくなるなって思ったりするんです。
だから私、生きてるうちにそういう沖縄を見たいですね。私が関わってる若者たちの中には、「家庭を持つ」っていうことが「意味が分
からない」って言う子もいます。「早く結婚したい、」「パートナーなんかいらない」っていう両極なんですね。
早く出産する子は「ゆるがない子と家族が欲しい」っていう層と、もう一方は「パートナーを持つっていうことの意味が分からない。」なぜなら自分がそんな家庭のモデルを知らないからって言ったりします。
だからパートナー持つ持たないは本人の選ぶことではあるんだけど、一緒に生きるパートナーって私いないよりはいた方がいいかなと思います。いない方がいいケースもあるけど1度はトライしてほしいなって思うの。そこ恐れずね。
そのためにはやっぱり支える手が18歳で終わりではなくて、その後もずっと必要だなって思っています。私、27歳の娘がいて、ずっとまだ家にいます。全然何にもしないわけ。27歳でもこれかっていう…。
だから自分の子供にできることを、目の前の他人の血の繋がってない若者にも同じようにできたら、なんかいい世の中になるなと思うんですけど。だからね棚原喜美枝みたいな人いっぱい増やしたいです。(笑)
あの時大変だった自分に何を声かけますか辛いことあるけど、これって意味のあることだよって言いたいですね。後で分かるからって。意味のあることが必ず起きてると思いますね。
だから不思議なんですけど、私、やりたいなと思ってることが向こうからやってくる感じがします。道が開けていくっていうか。すごいですよね、最近そう思うんですよ。
だから色々色々ありますけど大変なこともありますけど、多分必要なこと起きてるんだなと思ったりします。
一番大変だった時期
1番大変だったのは、施設の子供たちがものすごく荒れてる時期です。夜中に街中を子供たちを探しに行った時期があるんですよ。あの時すごい大変でしたね。
子供たちが中学生になるとものすごく荒れて、学校にも行かないし昼夜逆転するし、タバコは吸うしお酒は飲むし、夜中無断外出や徘徊をして、よその子を施設の中に入れ込んで泊まらせしまうような施設が崩壊した時期があるんですよ。あん時はものすごい大変でしたね。
そんな時に職員も少なくて、宿直明け宿直明けっていう2日に1回泊まらなきゃならないそれがずっと続くんですよ。そうすると1ヶ月で何回宿直したんだろうっていう時がありました。
それでも子供に付き合い続ける。本当だったら「もうあなたなんかいない方がいい、こっから出ていきなさい、」施設って別に血の繋がりもないから出そうと思ったら出せるし、さよならできるんですけど。そうせずにとにかく昼も夜も付き合い続けた時期はすごく大変だったなと思います。でもあれがあったから今、青年期になってる彼らが非常に可愛いですね。なんか表現方法がそれしかなかったよねって思います。
皆さんに伝えたいこと


大人であっても何十代になっても「なりたい自分になりましょう」っていうのはありますね。「なりたい自分に。」
例えばうちの職員みんな40代以上だったり30代が1人だけいるんですけど40代以上なんですけど、皆さん今すごく楽しそうにお仕事してくれてます。みんな自分の人生を楽しんでる感じが見られてて、皆さん本当に素敵だなと思ったりするんです。
だから大人であっても「「なりたい」自分になるために努力してる」人生楽しんでる人ってすごく子供たちにとっては居心地がいいみたいです。
大人同士の関係性ってすごく子供って見るじゃないですか。特にうちに関わる子たちはお家が機能不全であることが多かったので、大人の関係性をキャッチするアンテナが優れてるんですよね。
子供たちに教えないっていうのがいいかなって思います。
よくボランティアさんに「何かお手伝いできることありますか?」って聞かれることがあります。でそれって必ずしもうちの施設でボランティアすることではなくて、もしかしたら目の前の近くにいるこどもにお手伝いを少しだけやるっていうのでも随分違うと思うんですよね。
私も小さい時に家が大変だったので。両親はその弟の方に持っていかれて、私の幼稚園のお弁当会に母がお弁当作るの忘れて、お弁当持ってなくて泣きながら道端歩いてたら、近所のおばさんがどうしたって聞いてくれたことがあります。
「お弁当会なのにお弁当がない」って言ったら、おばちゃんがサンドイッチ作って持たせてくれたんですよ。今でも思い出に残ってるぐらいだから、すごいことですよね。子供食堂の始まり。
だからささやかなことで、こどもの手助けってできるんだなあと思います。多分皆さん1つや2つ多分あるんじゃないですか、近所のおばさんだったり親以外に関わってくれた大人、多分一人やふたりいるんじゃないかなと思ったりするんですよ。
付き合ってる時間の長さとかではなくて、自分を受け止めてくれた人が子供時代にあったかっていうのはすごく子供の育ちの中で大事なんだと思います。だからそれって親以外にもできることだし、すべての親にもこどもにも「ささやかな手」は必要だと思います。
阿部民子: 棚原さん、今日ありがとうございました。充実したお話を聞
けました。本当にありがとうございます。
棚原さん: こちらこそ振り返る機会が持てては良かったです。
阿部民子: 良かったですありがとうございました。
information
https://aru-okinawa.jp/
ばぁば保育園、託児サポーターボランティア募集中です!
お気軽にお問合せください。