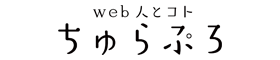ちゅらぷろインタビューvol.9人生のターニングポイントとこれからの夢
「すべての夫婦に孤独な子育てをさせない」沖縄発の新たな挑戦
NPO法人「未来きづなのたね」代表理事のみささん

NPO法人「未来きづなのたね」代表理事のみささんは、沖縄県を拠点に「すべての夫婦に孤独な子育てをさせない」という理念のもと、夫婦ふたりのための持続可能な絆づくりをサポートする活動を行っています。2023年11月22日「夫婦の日」に設立したばかりの団体ですが、その活動の背景には代表自身の経験が深く関わっています。
代表みささんのプロフィール
沖縄県在住で、中学2年生と小学2年生の男の子2人の母親であるみささん。彼女が夫婦関係のサポート事業を始めたのには、約10年前に自身が夫婦関係に悩んだ経験が大きく影響しています。
「夫と一緒に人生を歩むのは難しいんじゃないかと、誰にも言わずに心に秘めて、脳内離婚をずっと繰り返していた時期がありました」と当時を振り返ります。
夫婦関係改善のきっかけ

転機となったのは、異性間コミュニケーション協会が沖縄で開催したパートナーシップに関するセミナーでした。男女の違いやコミュニケーションの違いについて初めて本格的に学び、衝撃を受けたといいます。
「それまでの私に雷が打たれたような衝撃でした。こんなにも違うのかと。実は夫婦関係をこじらせていたきっかけは私にあったんだと気づきました。実は夫は私のことを大切に思ってくれていた、愛してくれていたんです」
その気づきから男女の関係性やコミュニケーションを学び始め、自分自身の夫への接し方を変えていくうちに、徐々に夫の態度も変わっていったと言います。冷戦状態だった家庭に会話が戻り、一緒にいることが楽しくなっていきました。
あれから7年経ちますが、日々、夫婦として家族として成長できる喜びと夫への感謝の気持ちが続いています。
NPO法人立ち上げの経緯
「これは本当にパートナーシップに悩んでいる人がたくさんいると思って、夫に『こういう仕事がしたい』と相談したら、『絶対やった方がいい。自分たちみたいに悩んでいる人はきっとたくさんいる』と背中を押してくれたのが活動のきっかけでした」
活動を始めて7年。コロナ禍ではオンラインを通じて沖縄県外や海外在住の日本人とも交流を深め、パートナーシップの悩みは国や地域を超えた普遍的な問題だと実感したそうです。
「日本人だけじゃない、沖縄の人だけじゃない。ベトナムの人も台湾の人もアメリカの人も、みんなパートナーシップに悩んでいる。これは本当に大切なことなんだと感じました」
沖縄の子育て環境と課題 離婚率全国1位の背景

沖縄県は離婚率が全国1位という現実があります。みささんはその背景に、子育て世代の孤立があると指摘します。
離婚率が最も上がる時期は、未就学児を育てている時なんです」と説明します。育児休暇中は行政や地域からのサポートが手厚く、母子のコミュニティも充実していますが、職場復帰後は相談相手が激減。子育ての悩みを誰にも相談できない孤独な状況に陥りやすいのです。
沖縄県の4人家族の平均年収は250万円と低く、離婚によって片親家庭になると経済的にさらに苦しくなります。それが子どもの貧困問題にもつながっていると言います。
「離婚率が上がれば一人親世帯が増え、県や国、市町村は母子手当を支給し、自立支援を行う必要がある。そこに大きな税金が使われてしまいます」
支援の空白期間
育児休暇中は手厚いサポートを受けられるものの、仕事復帰後に支援が途切れてしまう問題を指摘します。
「育児休暇中は90〜95%の人が『子育ての悩み、お金の悩み、健康の悩み、仕事の悩みを相談する相手がいる』と答えますが、育児復帰をするとこれが半分に減るんです」
仕事、子育て、家事に追われる日々の中で、夫婦の時間も取れなくなり、「夫は何もしてくれない」という不満が積み重なって離婚に至るケースが多いといいます。
「もう一つの道」を提案
みささんは離婚か我慢するかという二択ではなく、「もう一つの道」があると提案します。
自身が悩んでいた当時、「インターネットで『沖縄で夫とのコミュニケーションに悩んでいる』と検索すると、離婚相談所しか出てこなかったんです。どうやって上手く別れられるか、養育費が取れるかという情報ばかりで、夫婦関係を修復する選択肢がなかった」
その経験から、夫婦関係をリセットし、リスタートする可能性を伝えたいと言います。
「私はありがたいことに、もう一つの道を歩むことができました。夫と離れることもしなくてよかったし、子供たちを手放すこともしなくてよかった。自分自身の人生をもう一度スタートさせる喜びと夫婦ふたりで家族時間を豊かにする幸せを感じることができたんです」
親になるための学びの場の必要性
みささんは「最初から親になれる人はいない」と強調します。母親も父親も、子どもの成長と共に親として成長していく過程が必要だと言います。
「子どもが小学校、中学校と義務教育を受けられるように、私たち子育て世帯の大人たちも、大人になっていく階段を徐々に踏んでいく。子どもの成長と共に一緒に育っていくための環境づくり、リソースがこれからはとても大事だと思っています」
その思いから、特に夫婦ふたりで学ぶ場を提供したいと考えているそうです。
NPO法人「未来きづなのたね」の独自性

「実は夫婦ふたりのための学びの場を作るというのは、どこもやっていないんです」とみささんは言います。
「ママのための子育ての学びの場やパパのための学びの場はそれぞれ団体があちこちに設立されていますが、夫婦ふたりが同時に情報を受け取りアウトプットする場というのはないんです。全面的に夫婦ふたりのためにというところを押し出しているのは、うちの団体が初めてだと思います。」
役所からも「こういったプロジェクトは初めてですね」と言われるほどの新しい取り組みとして興味を持っていただいています。
個人的な挑戦 – 新たな家族のステージへ
インタビュー当時、みささんは新たな家族の試練を迎えようとしていました。夫が転勤で単身赴任となり、最低2年は帰ってこない状況になるのです。
「夫婦にとって今セカンドステージに入ったと思っています。夫がいない家庭で私は子育てをする。中2になる息子、思春期の男の子を抱えているこの時期は本当は父親が必要な時期ですが、父親がいないということは私がそれを担うということ。必然的に強くならないといけない」
そして2〜3年後、夫が戻ってきた時の新たな課題も予想しています。
「夫がいない中で家庭が出来上がってしまっている状況の中で、2〜3年後に夫が帰ってくる。その出来上がった家族の雰囲気の中に夫がどう入っていくのか、私がどう夫を受け入れるのか。また生活リズムが変わってきます。抜けるのは簡単ですが、抜けて入ってくるということがやはり試練です」
この経験をパートナーシップの講師としても貴重な学びにしたいと前向きに捉えています。
過去の自分へのメッセージ
「目の前にいる人を信じていいよ」と過去の自分に伝えたいと言うみささん。
「自分の殻に閉じこもってしまっていたので、もっともっと周りの人に甘えてもいいし、周りの人を信じて気持ちを開いてもいいんだよ」
読者へのメッセージ

「今、大切な人がいるということがものすごく幸せなんだということに気づいて欲しい」とみささんは締めくくります。「人を愛せるってものすごく幸せなことで、それは自分のことを大切にしているからその人を選んだと思うし、子供たちというギフトが届いていると思います。」
弱さを隠さず、助け合える関係性の大切さも強調します。「弱さというのは周りの人に助けてもらうためにある。もし自分の強みがあるなら、それはあなたが助けたいと思う人に使ってあげるといい」
「みんな違ってみんないい」という言葉と同じように、「みんな違ってみんな同じ」。これからも未来につながる絆づくりを一緒にやっていけたらと、読者への呼びかけで締めくくりました。
information
ホームページ https://www.sfba.or.jp
いい夫婦の日 イベント https://www.sfba.or.jp/lp/1122event/